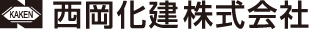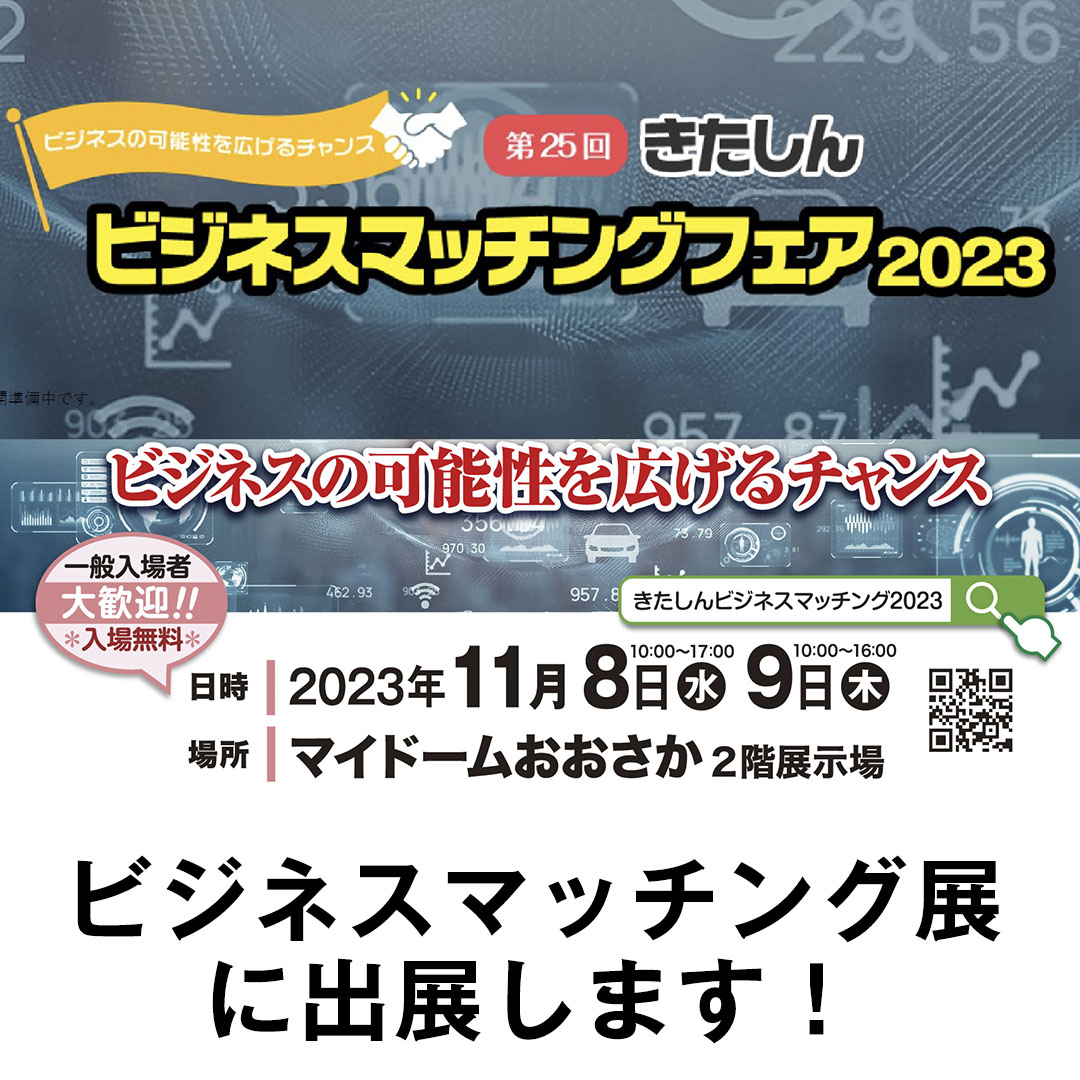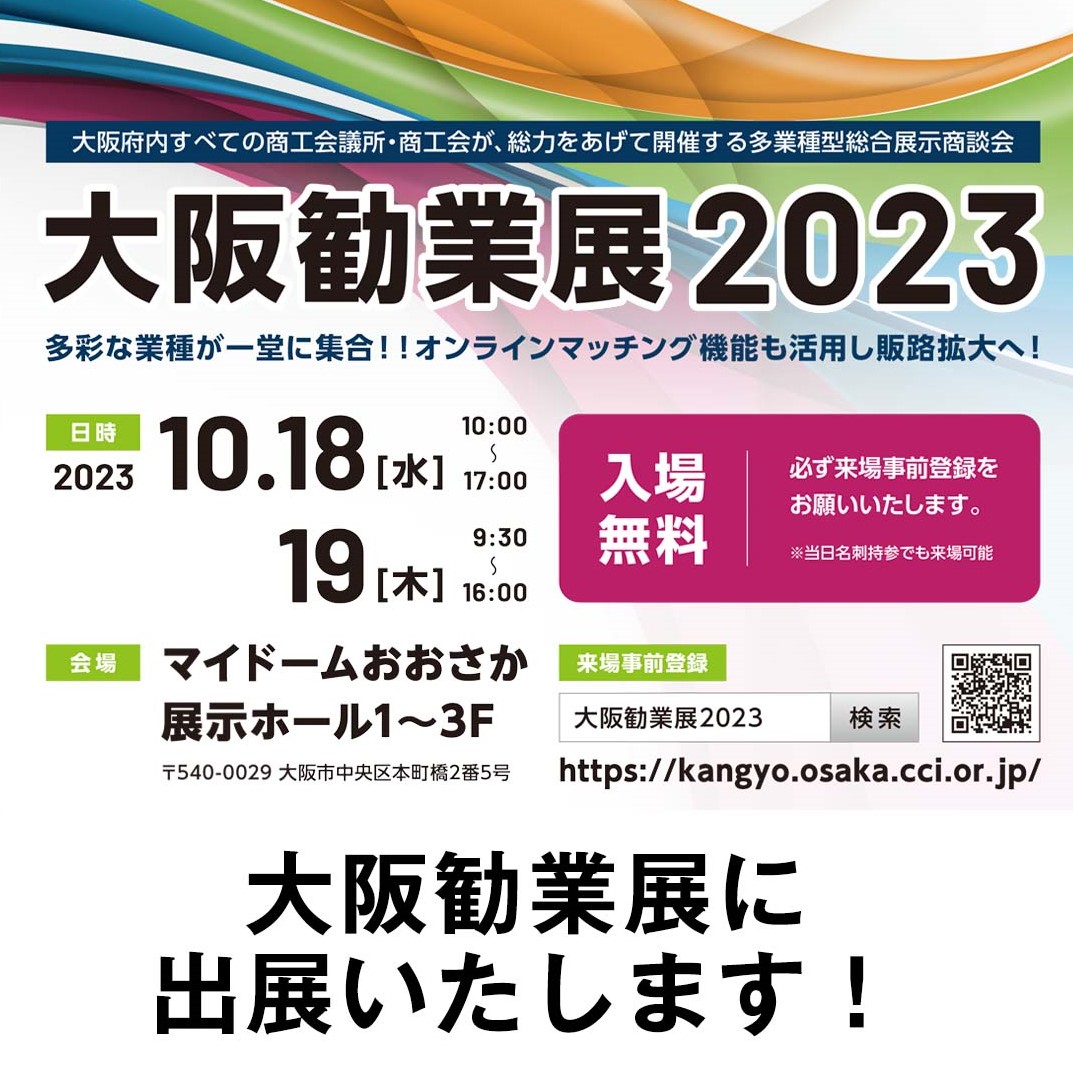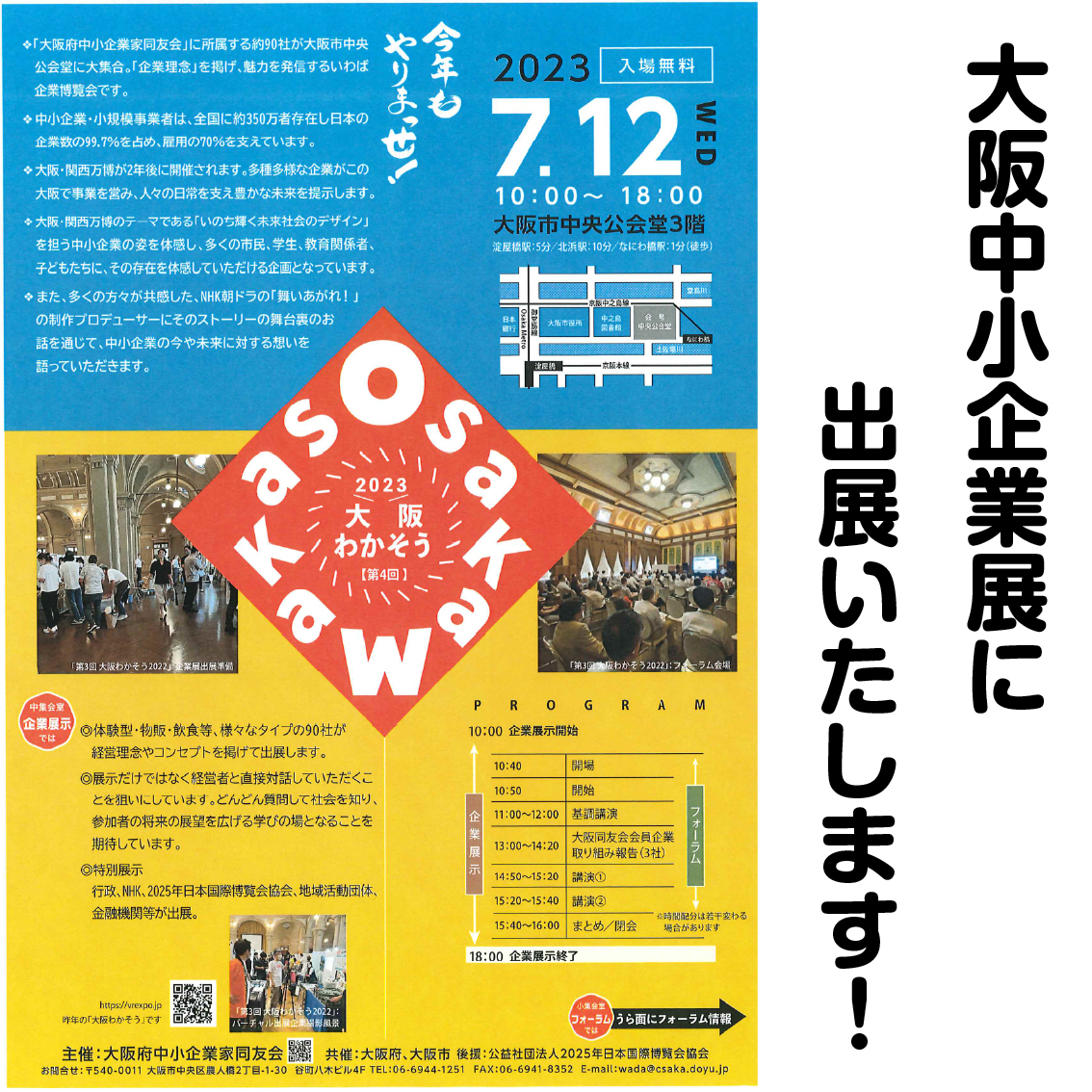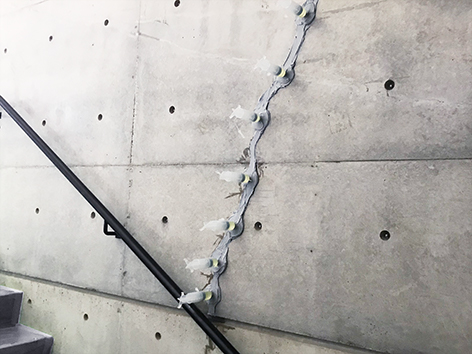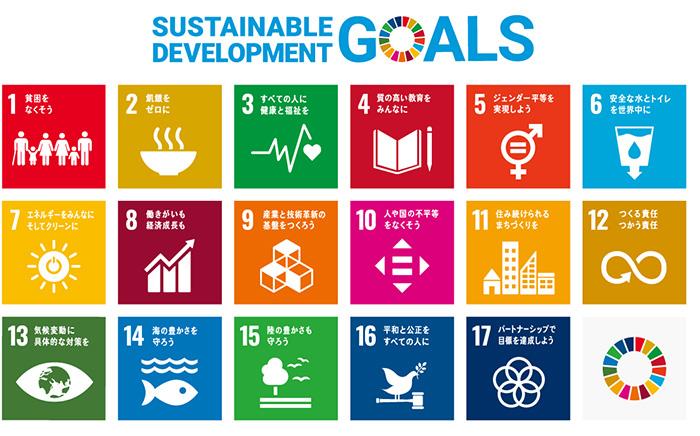NEWS & TOPICS
-
2024-03-21
-
2023-12-14
-
2023-10-03
-
2023-06-19
Corporate information
現地調査、ご質問やご要望等何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
西岡化建株式会社
TEL:072-643-1125
(受付時間:月曜~金曜(祝日除く) 9:00~18:00)
FAX:072-643-1127
(受付時間:月曜~金曜(祝日除く) 9:00~18:00)
FAX:072-643-1127
Achievements
-
2022年10月
-
2022年2月
-
2022年8月
-
2022年3月
-
2021年10月
-
2020年8月